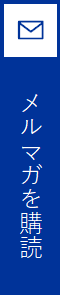コラムカテゴリー:DX(デジタル・トランスフォーメーション), 技術, 業界動向
最近、業務ヒアリングをしていると、IT部門ではない方でも「API」という用語を使う場面が増えてきました。さらに、経営層の方々からも「APIを使えば簡単にデータをやり取りできるのではないか?」という声が増えてきています。
APIという技術が広く知られるようになってきたことを感じますが、一方で「APIさえ使えばどんなシステムでも簡単に連携できる」という誤解も見受けられます。まるで魔法のように捉えられがちですが、実際にはそうではありません。APIを活用するにはコストや技術的な課題が伴い、すべての連携において最適な方法とは限りません。
API連携の現実
API(Application Programming Interface)とは、異なるシステム同士で情報を交換する仕組みですが、すべてのシステムで簡単に連携できるわけではありません。例えば、APIがそもそも用意されていないシステムでは、連携自体が不可能です。特に、古いシステムや一部の業務用ソフトでは、APIが提供されていないことが多いです。この場合、別の方法を使ってデータをやり取りする必要があり、例えばCSVファイルを使って情報をインポート・エクスポートしたり、作業を自動化するツールを使ったりします。
また、APIがあったとしても、その仕様(使い方)が限られている場合もあります。その結果、必要な情報が取れなかったり、思うように機能が使えなかったりすることもあります。
API連携は万能ではないため、どこまで実現できるのかをしっかり理解することが大切です。
API未連携=効率が悪いという誤解
非IT部門の中には、「API連携していないシステムは非効率だ」と感じているケースがあります。特にベンダーや外部から「API連携で効率化できます」といった提案を受けると、「連携していないシステムは時代遅れだ」と思いがちです。しかし、これは一面的な考え方です。
API連携には開発や運用にかかるコストがあります。APIを活用するにはシステムの仕様調査や開発作業が必要となり、場合によっては数百万円の費用がかかることもあります。また、連携後も仕様変更への対応や障害対応など、運用面での負担が発生することがあります。
単に「APIがないからダメ」と考えるのではなく、「コストに見合う効果があるか」を考えることが重要です。
API連携にこだわるべきか?システム全体を見た選択肢
API連携は便利な手段ではありますが、システム全体を見ずに個別のシステム同士でAPIを使うと、管理が難しくなることがあります。システム同士を直接つなぐと、それぞれが依存し合ってしまい、全体の運用が複雑になることもあります。こうした場合、EAI(Enterprise Application Integration)を活用して、システム全体を疎結合化するアプローチを検討するのも有効です。
EAIは、各システムを直接結びつけるのではなく、一元的なデータ連携基盤を通じて情報をやり取りする仕組みです。これにより、個々のシステム同士の直接的な結びつきを減らし、システム全体の柔軟性を向上させることができます。また、新しいシステムを導入する際にも、既存のシステムと直接連携するのではなく、EAIを通じてデータをやり取りすることで、影響を最小限に抑えることができます。さらに、EAIを活用することで、データ連携のジョブ管理を統合しておこなえるため、監視や障害対応の効率が向上し、システム運用の負担を軽減することが可能になります。
システム連携の選択肢を適切に考える
APIがあるからといって、それを必ずしも利用しなければならないわけではありません。API連携は強力な手段ですが、その実装にはコストや運用面での課題が伴います。また、すべてのシステムがAPIによる連携に適しているわけではありません。自社のシステムがAPI連携していないからといって、それが問題とは限らず、費用対効果を考慮した上で、適切な連携手段を選択することが重要です。
APIを活用するか、それともEAIを導入するか、あるいは他の手段を選ぶかは、業務要件やコスト、運用負荷などを総合的に判断して決めるべきです。重要なのは、個別の技術に固執せず、会社全体のシステムを見渡して最適な選択をすることです。
2025年03月24日 (月)
青山システムコンサルティング株式会社